昔の日本酒、今の日本酒:驚きの違い
はじめに
みなさんは「日本酒」と聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか?
澄んだお酒、フルーティーな香り、洗練された味わい…。きっとそんな印象を持つ方が多いのではないでしょうか。
けれども、日本酒の長い歴史をひも解くと、今の常識では考えられないような意外な姿が見えてきます。日本酒は、時代ごとの文化や技術、人々の暮らしとともに形を変えてきたのです。

三重県明和町に蔵を構える旭酒造は、明治八年の創業以来、伝統を守りつつ酒造りを続けてきました。伊勢神宮ゆかりの地で受け継がれる味わいには、歴史の息づかいが宿っています。
今回は、日本酒の歴史の中で生まれた「昔の常識」と「現代の常識」の違いを、5つの視点からご紹介します。日本酒の奥深さを再発見する小さな旅に、ご一緒いただければ幸いです。
驚きの真実1:口噛み酒から始まった
最も古い日本酒の一つは「口噛み酒」です。
その名のとおり、米や穀物を人が口で噛み、唾液に含まれる酵素で糖に変え、自然発酵させて造ったお酒。現代の感覚では驚いてしまう方法ですね。
縄文時代から弥生時代にかけて稲作が広まった頃、まだ「麹」という存在が知られていなかったため、この方法が唯一の手段でした。神事として巫女などが口噛み酒を造り、神に捧げていたとも言われています。
今では考えられないやり方ですが、当時の人々にとっては神聖な儀式の一部だったのです。

驚きの真実2:水へのこだわりは後から
「日本酒は水が命」とよく言われます。
現代では仕込み水の硬度やミネラル、清浄度にまで徹底的にこだわりますが、昔はそうでもありませんでした。
江戸時代以前は「きれいな水ならよい」程度の認識で、科学的な水質分析などはもちろんありません。転機となったのは江戸時代、灘の「宮水」が酒造りに適していると発見されたことでした。
そこから「水の質が酒の味を左右する」という考え方が定着し、現代の常識につながっていったのです。
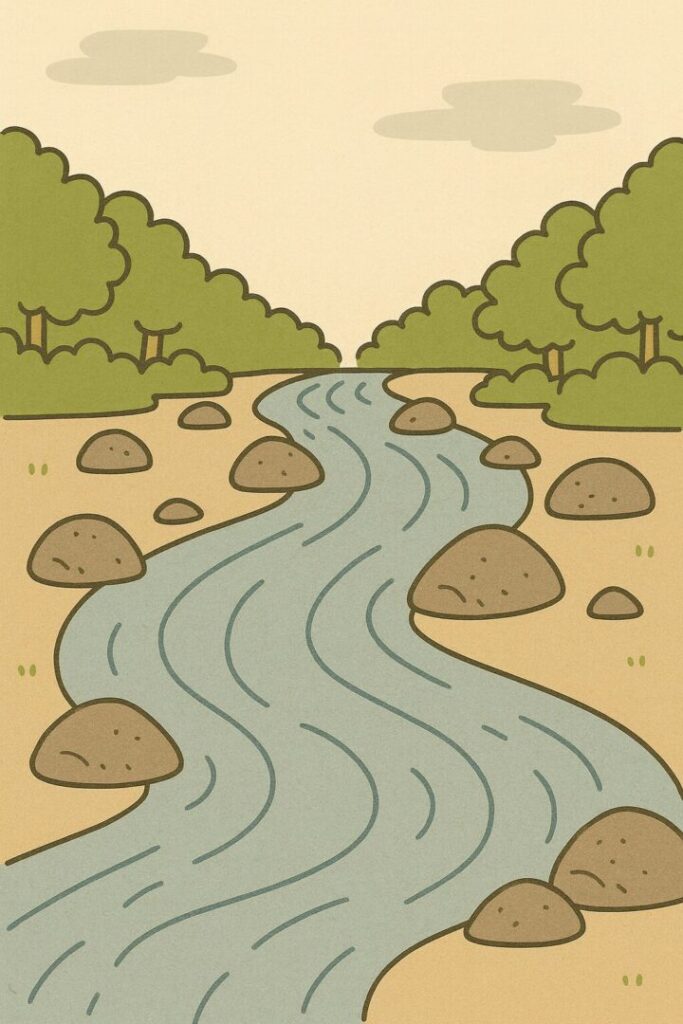
驚きの真実3:昔のお酒は黄金色?
現代の日本酒は透明で澄んだ見た目が多いですが、昔のお酒は必ずしもそうではありませんでした。
琥珀色や黄金色をしたお酒が好まれた時代もあり、古文書にも「琥珀色の美酒」といった記録が残っています。これは、当時の技術では不純物を取りきれず、熟成によって自然に色がついたためです。
今では「透明=きれいな酒」という価値観がありますが、昔の人々にとっては色のある酒がむしろ魅力だったのです。

驚きの真実4:神に捧げる酒から日常の酒へ
日本酒は長い間、神聖な存在でした。
神話にも登場し、奈良時代には宮中の儀式で造られるほど。まさに神と人をつなぐ大切な役割を担っていました。
しかし、室町時代以降になると商業や技術が発展し、日本酒は庶民の生活にも広がります。祭りや祝い事、日常の晩酌へと、日本酒の存在は大きく変わっていきました。
今のように「嗜好品」として楽しまれるようになったのは、この時代からなのです。
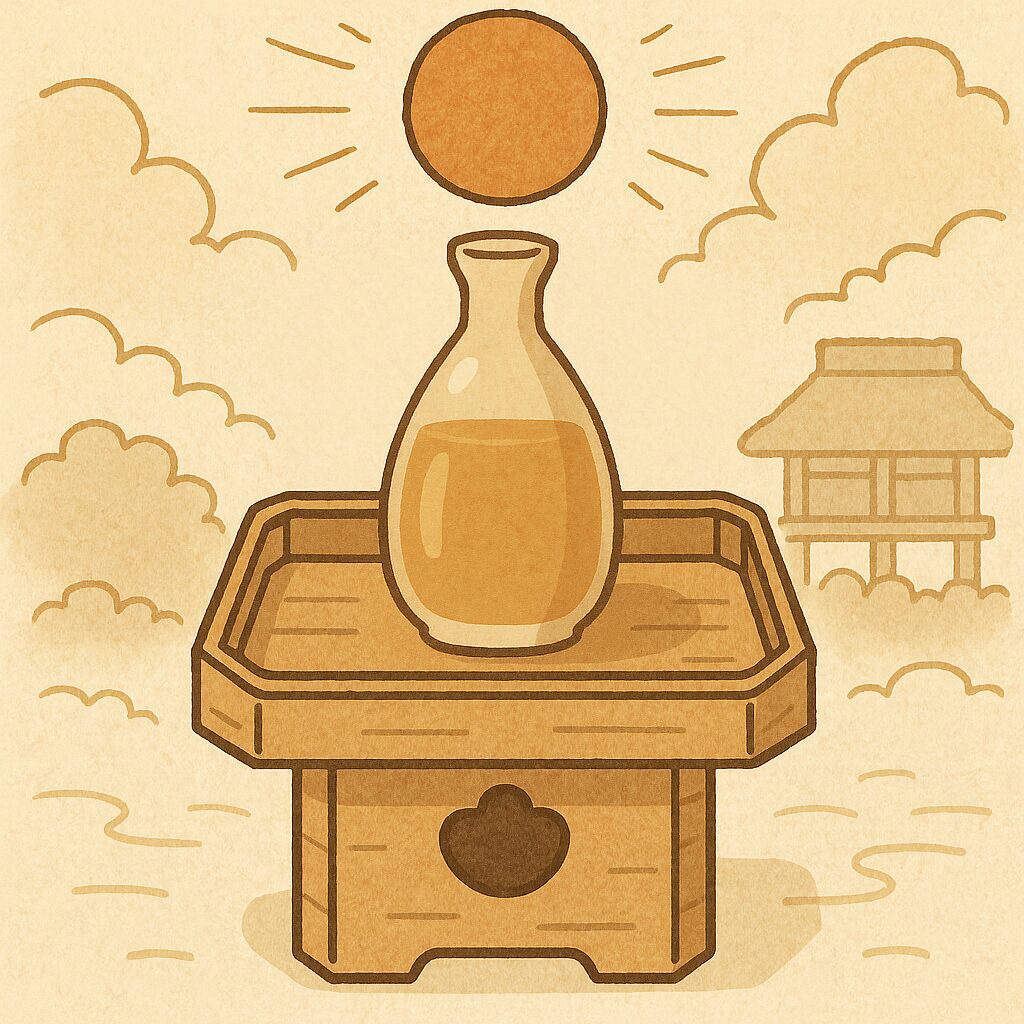
驚きの真実5:等級制度の不思議
今の日本酒には「純米大吟醸」「吟醸酒」など、特定名称による分類があります。
ですが戦後から平成初期までは「特級・一級・二級」という等級制度でした。
これは酒税の基準として決められていたもので、必ずしも品質を正しく表すものではありません。純米酒が低く扱われることもあり、今から考えると不思議な仕組みです。
1992年にこの制度は廃止され、現在の「品質を重視した分類」に移行しました。日本酒の評価基準が大きく変わった瞬間でした。

おわりに
口噛み酒から始まり、水や色、神事との関わり、等級制度の変化…。日本酒の歴史には、現代から見ると驚きの真実がたくさんあります。
三重県明和町の旭酒造は、こうした歴史や伝統を大切にしながら、現代の技術と匠の技を融合させ、日々酒造りを続けています。
旭酒造のお酒を味わいながら「昔の日本酒はどんな姿だったのだろう」と思いを馳せるのもまた一興。歴史を知ることで、一杯のお酒がより深く、豊かに感じられるはずです。

商品をお買い求めされたい
方はお問い合わせください。


